




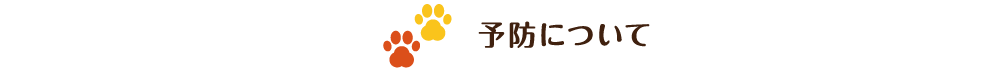

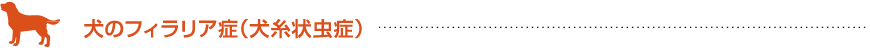
フィラリア症は、蚊の刺し傷から感染した小さな幼虫が体内を移動しながら成長し、最終的には心臓(肺動脈)に15~30cm程度の大きさの成虫となって寄生するという病気です。この病気は、蚊によってうつされるちいさな虫が、成虫へと成長してしまう前に駆虫することで予防できます。飛んでいる蚊がいつでもフィラリアをうつすわけではなく、感染が成立するには一定の気温条件が必要になります。この特徴を利用して、フィラリアに感染する恐れがある期間を気温から推定することができます。この方法によれば、大阪の感染期間は、毎年5月中に始まり11月中に終了しています。フィラリア予防薬は蚊に刺された後に駆虫をするお薬ですので、予防薬の投与が必要になる期間は、この感染期間から1ヶ月遅れの6月から12月までとなります。当院では開始時期に少し余裕をもった5月下旬からの予防開始を推奨しています。フィラリア症にかかった状態で予防薬を飲むと、副作用がおこる可能性があります。そのため、毎年フィラリアの予防を開始する前には、フィラリアに感染していないかどうかを確認する血液検査を実施しています。
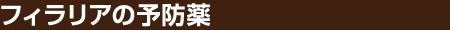
錠剤、おやつタイプ、スポットタイプ、注射などがありますが、当院では主に錠剤とおやつタイプを使用しています。ノミ・マダニとフィラリアが一度に予防できる、おやつタイプのお薬も発売されました。
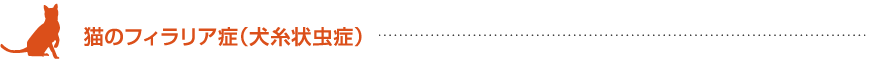
最近では、猫もフィラリア症の予防をしておいた方がいいと考えられるようになってきています。フィラリア(犬糸状虫)はイヌ科の動物に寄生する寄生虫ですので、猫が蚊に刺されたとしてもフィラリアに感染する確率は犬と比べれば低いものです。しかし、猫の10頭に1頭以上でフィラリアの感染歴が見つかり、そのうち39%が完全な室内飼育であったという報告もあり、予想していたよりも高率で感染しているのではないかと考えられるようになっています。感染を受けた猫は、食欲不振、元気消失、嘔吐、呼吸困難、咳などの様々な症状を示す可能性があります。しかし、約30%は無症状だといわれており、元気だった猫の突然死では、フィラリア症も疑う病気の一つとしてあげられています。診断は困難なことが多く、犬と同じ簡易な検査では通常は検出することができません。どうしても診断の必要がある場合には抗体検査を行いますが、確定できない場合もあります。

猫のフィラリア症の予防には、1ヶ月に1回、背中につけるスポットタイプのお薬をご案内しています。予防が必要になる期間は犬と同じ5月下旬~12月までです。
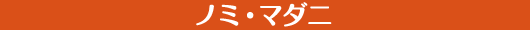
ノミやダニからペットを守るには定期的な対策が必要です。ノミの被害が多いのは3月後半から11月までです。また、大阪でマダニの被害があるのもこれとほぼ同じ期間です。少なくともこの期間はノミ・マダニの予防が必要になります。マダニは野外で付着するために、この期間以外の時期に寄生されることはありませんが、ノミは動物が集まる暖かい場所であれば真冬でもうつる可能性があります。そのような場所によく連れて行くのであれば、一年を通しての予防が必要です。ノミやマダニの寄生は、刺された場所に皮膚炎を起こす以外にも様々な問題を起こす可能性があり、それらの中には人間にも感染する感染症も含まれます。
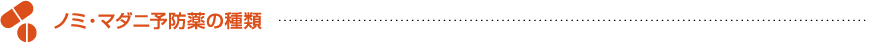
予防には、従来からある皮膚に塗布するスポットタイプのお薬に加え、おやつタイプのお薬の取り扱いも始めました。スポット薬をつけるのを嫌がる、動いてスポットしづらい、皮膚が弱いなどの理由でスポットタイプのお薬が使いにくかった子には、こちらをおすすめします。

主にウイルスによる伝染病を予防することが目的です。接種するワクチンの種類は、ガイドライン等で必ず予防することが推奨されている病気(コアワクチンといいます)が含まれるようにし、その他の病気のについてはライフスタイルや地理的環境に応じて必要なら追加するという考えで選択します。注射後3日間は激しい運動やシャンプーを避けて下さい。
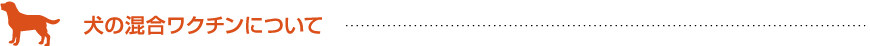
自宅周辺からあまり遠くへは連れて行かない場合は、すべての子犬に対して接種が推奨されている、ジステンパー、アデノ、パルボの3種類を網羅している5種混合ワクチンを選択しています。自然の多い郊外やアウトドアへよく連れて行くような場合や、レプトスピラ症が好発する地域へ行く可能性がある場合は、5種に加えてレプトスピラを含んだタイプのワクチンをおすすめしています。
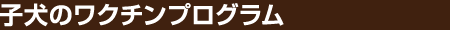
生後6~9週齢で初回のワクチンを接種し、その3~4週後に2回目を接種、14~16週齢で3回目の接種を行います。10週齢終了可能なプログラムを推奨する製品がありますが、できるだけ14~16週齢で3回目の接種を行うことが推奨されています。その後は1年毎に接種します。なお、動物愛護管理法の改正により、8週齢未満の販売ができなくなったため、初回のワクチンはすでに済んでいる場合がほとんどです。

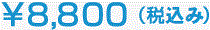
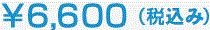
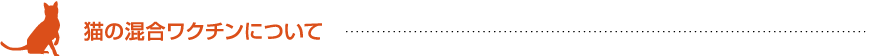
完全室内飼育なら3種混合ワクチン、屋外へ出る可能性があるならそれにFeLV(猫白血病)を加えたタイプのワクチンをおすすめします。ただし、FeLVについてはすでに感染している個体にワクチンを接種する意義はありませんので、接種の前にFeLVに感染しているかどうかを確認する血液検査が必要です。
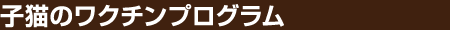
6~8週齢で初回のワクチンを接種、その後3~4週間隔で2~3回接種します。その後は1年毎に接種します。屋内だけで飼育されている場合は、すべての子猫に接種が推奨されている、猫汎白血球減少症、猫カリシ、猫ヘルペス1型を含む3種混合ワクチンを選択しています。他の猫に接触する機会があるなど、猫白血病ウイルス(FeLV)に感染するリスクがある場合には、3種に猫白血病を加えたタイプのワクチンを選択しています。


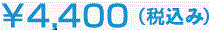
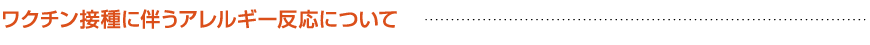
ワクチンを接種したあとにアレルギー反応を起すことがあります。これは接種をするたびに発生する可能性があるため、前回のワクチンで大丈夫だったからといって、次も大丈夫だとはかぎりません。顔の腫れ、痒み、紅潮、下痢、腹痛など様々な症状を示します。これにショック症状(血圧低下)が加わった、アナフィラキシーショックという危険な反応を示す場合もあります。アナフィラキシーショックの多くは接種後30~60分以内に発生し、血圧低下に伴って、嘔吐、元気消失、重度の場合は意識障害などの症状が認められます。この状態に陥った場合には迅速な治療が必要です。この問題に備えるために、接種後30分程度は院内で様子を見ていただいたり、病院にすぐ戻れる場所で観察をしていただくことが望ましいといえます。ワクチンの接種は、アレルギー反応の出現ができるだけ夜中にならないよう、なるべく午前中の接種をお願いしています。他にワクチンによる副反応として、注射部位の腫れ・痛み・肉芽種形成、ワクチン関連性肉腫の発生、食欲不振、微熱、リンパ節の腫れなどがあります。

狂犬病予防法により、生後90日を超えた犬では、自治体への登録と年1回の狂犬病ワクチンの接種が義務付けられています。大阪市内で飼育されている場合には、当院で済み票発行、登録などの事務手続きを代行しています。その他の地域にお住まいの場合は、注射済み証明書を発行しますので、管轄する自治体で手続きを行なってください。2月は年度末にあたるため注射を実施しておりません(海外へ渡航する場合の接種は除きます)。
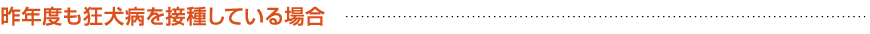
毎年1回、3月2日から6月30日の間に狂犬病予防注射を受けてください。10月など遅れた時期に毎年注射をしている方がいらっしゃいますが、この例であれば毎年6月から10月までの間は未接種扱いとなります。必ず指定された期間に接種してください。
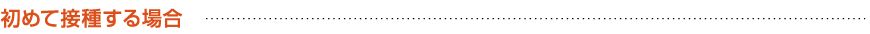
初回接種の場合は、犬を取得した日(または生後90日を超えた日)から30日以内に登録と注射を受ける必要があります。

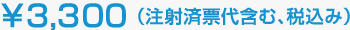 初めて登録される方は別途登録料¥3000が必要です。
初めて登録される方は別途登録料¥3000が必要です。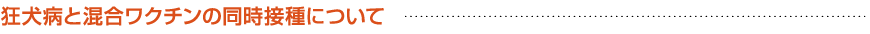
当院では、原則として狂犬病ワクチンと混合ワクチンの同時接種は行っておりません。添付文書の記載どおり、狂犬病ワクチンの後は1週間以上、混合ワクチンの後は4週間以上の間隔をあけて他のワクチンを接種します。
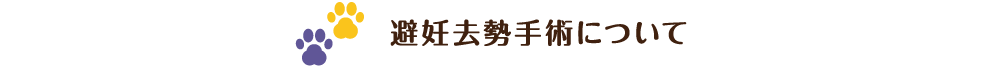
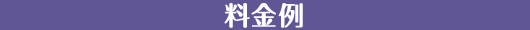
*税込み
| 猫 | 去勢手術 | ¥18,700 |
|---|---|---|
| 避妊手術 | ¥28,050 |
| 犬 | 去勢手術(体重6kgまで) | ¥26,400~ |
|---|---|---|
| 避妊手術(体重6kgまで) | ¥34,100~ |
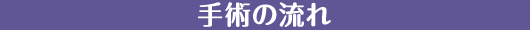

当日の朝11時までにご来院いただき、体重測定、問診、聴診などの身体検査、鼠径ヘルニア、臍ヘルニア、乳歯遺残の確認、ご連絡先の確認などを行ったうえお預かりします。その際、手術に関する疑問点などは遠慮なくご質問ください。

検査の結果、麻酔の実施に影響するほどの問題が認められた場合にはご連絡いたします。高齢犬や持病のある動物の場合は、当日ではなく事前の検査とさせていただいております。

血管の確保、鎮痛薬の先制投与などを行います。

麻酔前投与薬、抗生剤などの投与を行います。また、バイタルサインを取るための様々なモニタリング機器を装着し、静脈点滴を開始します。静脈内へ注射麻酔薬を投与して気管チューブが挿管できたら、吸入麻酔(ガス麻酔)で麻酔を維持します。

手術部位の剃毛と消毒が終わったら、手術を開始します。

手術が終わったら麻酔を切ります。目が醒めてきたら気管チューブを抜きます。ある程度覚醒したら入院室へ移動して観察を続けます。

19:00頃にお迎えに来ていただきます。その際、術後の注意点についてご説明します。

術創の確認をしていただき、異常がなければ通院や消毒の必要はありません。
術後10日以上経過したら抜糸が可能です。
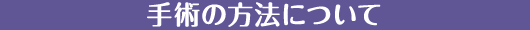
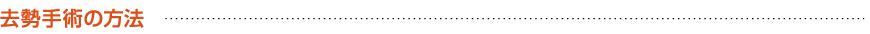
去勢手術では、陰嚢内にある睾丸を摘出します。陰嚢に近い皮膚を切開して睾丸を1つずつ体外に露出させ、精管と動静脈を吸収糸で結紮するか超音波メスで切断します。吸収糸で皮下を縫合、さらに皮膚を縫合して終了です。猫では開放創のまま終わります。
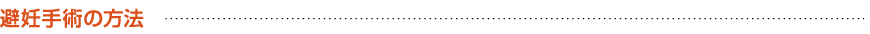
避妊手術として、当院では卵巣子宮摘出術を行います。お腹の正中の皮膚をメスで数センチ切開して腹壁(白線)を露出し、白線に切開を加え開腹します。子宮を牽引して一部を体外へ引き出します。卵巣と子宮の動脈を吸収糸または超音波メスで止血したら、卵巣提索、子宮頚管、子宮広間膜を切断して子宮を摘出します。吸収糸で腹壁および皮下組織を縫合し、さらに皮膚を縫合して終了します。

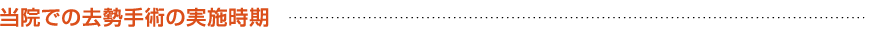
生後6ヶ月以降を推奨しています。
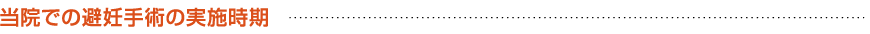
生後5~7ヶ月齢(初回発情前)を推奨しています。
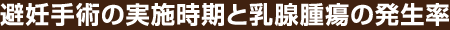
乳腺腫瘍の発生率は、未避妊犬の発生率を100%とした場合、以下のように報告されています。
| 初回発情以前に避妊手術を実施 | 0.5%(原文どおり) |
|---|---|
| 発情2回目以前に避妊手術を実施 | 8% |
| 発情2回目以降に避妊手術を実施 | 26% |
乳腺腫瘍の発生率について以前から上記のように言われていますが、この数字の根拠はあまり説得力のあるものとは言えないという趣旨の報告がされています。数字自体が合っているかどうかの議論は置いておくとして、早期に避妊手術を実施した個体に乳腺腫瘍の発生がきわめて少ないということは、私たちの経験上間違いありません。
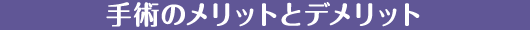
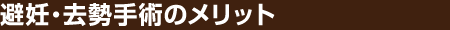
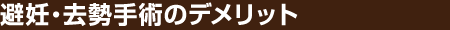

避妊去勢手術の実施には全身麻酔が必要になります。麻酔は手術の痛みから動物を守るためにどうしても必要な手段です。麻酔薬や管理技術の進歩、ペインコントロール(痛みの管理)の実施などにより、以前に比べて麻酔の安全性はかなり向上していると感じますが、それでも合併症や死亡のリスクはゼロではありません。少し古いですが、1996年に発表されたカナダの動物病院における麻酔による死亡率は、犬で0. 11%、猫で0. 1%であったと報告されています。当院では麻酔に関連する合併症の発生防止に最善の努力をしていますが、それでも合併症が起こる可能性がゼロになるとは言えません。万一、麻酔による合併症が疑われた場合には速やかに対処し、救命の努力、および後遺症を最小限にする努力をいたします。

縫合糸反応性肉芽種は、手術に使用した縫合糸に対して体が過剰な異物反応を起こした結果として腫瘤病変が形成されるものです。手術用の縫合糸として以前はよく絹糸が使用されてきましたが、絹糸は特にこの反応が起こりやすいため、当院では原則として使用しておりません。しかし、絹糸以外の縫合糸やレーザーメス、超音波メスなどを使用した場合の発生も報告されており、100%完全に予防することは無理のようです。当院では、できるだけ吸収糸を使用する、縫合糸を使用せずに機械を用いた切断や止血を行うなどの取り組みにより、縫合糸肉芽種の発生を最小限にする努力をしています。